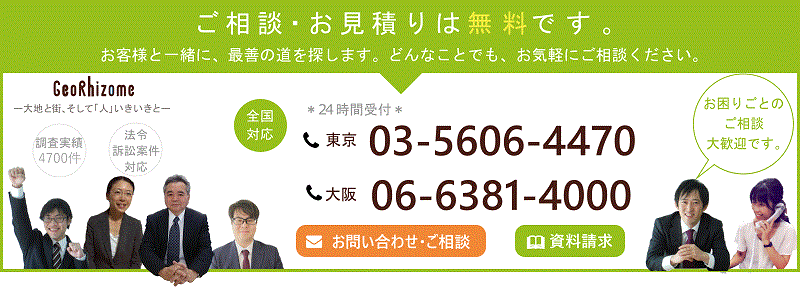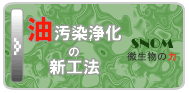土壌汚染調査の中で、土地の売買を目的とする調査を自主的に実施するケースがほとんどを占めますが、調査する当事者としてはコストも抑えておきたいところがあります。そんな中で、確実に汚染の可能性が少ないところで、農薬類の分析のみを外す場合もあります。なぜなのでしょうか? (農家の方へ。いつもおいしい野菜ありがとうございます。)
土壌汚染対策法の中にある基準に含まれている項目で農薬は5種類ほど存在しており、有機リンを除き1971年に使用が禁止されています。また、本物質の特性で残留性が低く、農場で使用されていても約1年もすれば無害化されるケースが多いです。
よって、調査項目から外しても問題がないという認識です。無論、農薬を製造するもしくは、薬剤を多く保管しているような場所では、調査を見送るわけにはいきませんが、我々としても無用なコストは掛けずに調査を進めることができればよいと考えています。
ジオリゾームにご相談ください。
TU
~~~2024年11月29日追記~~~~
第三種特定有害物質 農薬の「半減期」について
皆さんこんにちは。
土壌汚染調査を行うにあたり、調査対象地の過去の使用用途などを基に調査対象物質を決めるのですが、農薬類は分析項目から外す場合が多くあります。実際に調査計画を提出した際にお客様に「農薬は調査しなくてもいいのか?」と疑問を持たれることが多いため、理由について改めて解説しようかと思います。
まず、土壌汚染対策法で規定されている特定有害物質は、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第二種特定有害物質(重金属類)、第三種特定有害物質(農薬類+PCB)の三種類に区分されており、このうち第三種特定有害物質に、農薬として使用される「シマジン」、「チウラム」、「チオベンカルブ」、「有機リン」が項目として含まれています。こちらの4種の対象物質は、過去に農業を営んでいた土地であっても調査項目から外す場合があるのですが、それはなぜでしょうか?
その大きな理由として、地中での農薬の「半減期」が関わってきます。
一般的な農薬は、時間の経過とともに土壌中で分解が進んでいきます。土壌表面では太陽光などの作用で分解され、土壌中では微生物などの作用で分解されていくため、過去に使用していたとしても土壌中に長く残留していることはありません。
では農薬は散布してからどのくらい土壌中に残留するのか?といった部分が気になると思いますが、農薬の「半減期」(散布直後の農薬濃度が半分以下になるまでの期間)は、ほとんどが数日から100日の範囲にあり、比較的早く土壌中で分解されていく傾向があります。そのため、土壌調査対象地で過去に田畑を営んでいた履歴があったとしても、使用されていない期間が長いほど成分はほとんど残っていない傾向があるため、分析をしても検出されることは非常にまれなのです。
そのため、第三種特定有害物質の農薬類については、直近で農薬の使用履歴が無い限り調査項目から外すことが多いのです。お客様の調査費用を抑えるためにも、汚染のリスクを判断して調査項目を絞ることがあります。
疑問点やご相談がございましたら、いつでもお問い合わせください。
ジオリゾーム 瀬戸
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。